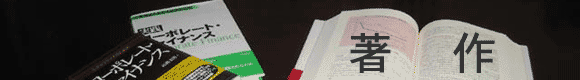王子による北越に対する敵対的TOBは、企業のステークホルダー(利害関係者)による敵対的買収に対する反発によって失敗した。
王子による北越に対する敵対的TOBは、企業のステークホルダー(利害関係者)による敵対的買収に対する反発によって失敗した。
証券アナリストの発言にもあるように、王子の北越との経営統合提案は経済的メリットの大きいものであった。北越の三輪社長は「王子が北越の高い生産性による利益を一方的に享受するにすぎない」と述べているが、将来の合併メリットを先取りした株価で北越の既存株主が北越株を売却できる限り、北越の株主にとって不利益にはならない。王子の経営統合提案に対して、北越側も株主価値向上策を発表するに至るが、それでも三輪社長の発言を見る限り、株主の利益という観点が基本的に欠けているように思われる。
もっとも、北越の多くの株主はTOBに応じなかったので、純投資目的の株主ではなかったといえる。その意味で今回のTOBは株主構成から考えて成功する可能性は低かったのかもしれない。結局、北越の経営はこのようなリレーションシップ(長期的関係構築)動機の安定株主の支持のもとで築かれてきたものであり、三輪社長の発言もその反映である。
北越の従業員も王子によるTOBには反対した。今後、日本で敵対的買収が盛んになるかどうかを考える場合、従業員の態度も大きな問題になる。伝統的な日本企業の従業員は勤務先に長い間コミットして、一種の投資を行っているので、その投資を回収できるようになるまでは経営体制や勤務体系が変わることを好まない。若い頃は生産性よりも低い給料で働き、年をとると生産性を上回る給料をもらうという伝統的な年功給はその一例である。日本では経営者のほとんどは内部昇進で選ばれるので、この問題に関しては、従業員と同じ立場に立つことになる。
現在、多くの企業はこのような極端な年功給の見直しを進めている。これによって従業員の企業に対する考え方が変わり、労働力の流動化も進む可能性がある。わが国において敵対的買収は、従業員の帰属意識がそれほど高くなく、労働力の流動性が高いような業種から起こるのではないだろうか。
最近、買収防衛策としての株式持ち合いが復活しているといわれる。これは株主価値経営が浸透したとはいわれるものの、結局、多くの日本企業の経営者は株主の利益を本当には考えていないことを示しているように思われる。
現在、多くの企業が買収防衛策を導入しているが、買収防衛策の意味するものも欧米と日本では全く異なっている。米国では買収防衛策は株主の利益になるように買収側との条件交渉をするための手段として位置付けられているが、北越の例が示すように、日本では買収価格にかかわりなく、買収を阻止し、現経営陣を守るための手段として位置付けられている。
最近の日本でのいくつかの敵対的TOBの失敗は、敵対的買収に反対する企業のステークホルダー(企業の利益関係者)の声が強いことを改めて印象づけた。しかし、敵対的買収なくして、企業再編や企業再生を効率的に行えるであろうか。わが国では製紙業界のように、設備が過剰であったり、企業数が多すぎる業界がいくつか存在する。かつてはそのような業界では、旧通産省や銀行が主導して業界再編が行われた。政府や銀行の役割が低下した現在では、その役割は資本市場に期待するしかない。敵対的買収がすべて成功したり、買収後の経営がすべてうまく行くことはあり得ないが、敵対的買収の脅威が、業界再編を促す効果を持つことは確かである。事実、今回は王子主導による業界再編そのものは失敗したが、結果的に日本製紙、北越製紙、三菱商事による再編を促すという効果があった。
このように考えると、今回の事件が契機となって、敵対的買収に否定的な空気が産業界に蔓延するようであれば、日本経済の利益にはならないのではないだろうか。
(第2章「王子製紙の北越製紙に対する敵対的TOB」(髙橋文郎執筆)から抜粋 )
|